紅茶製造についてRECRUIT
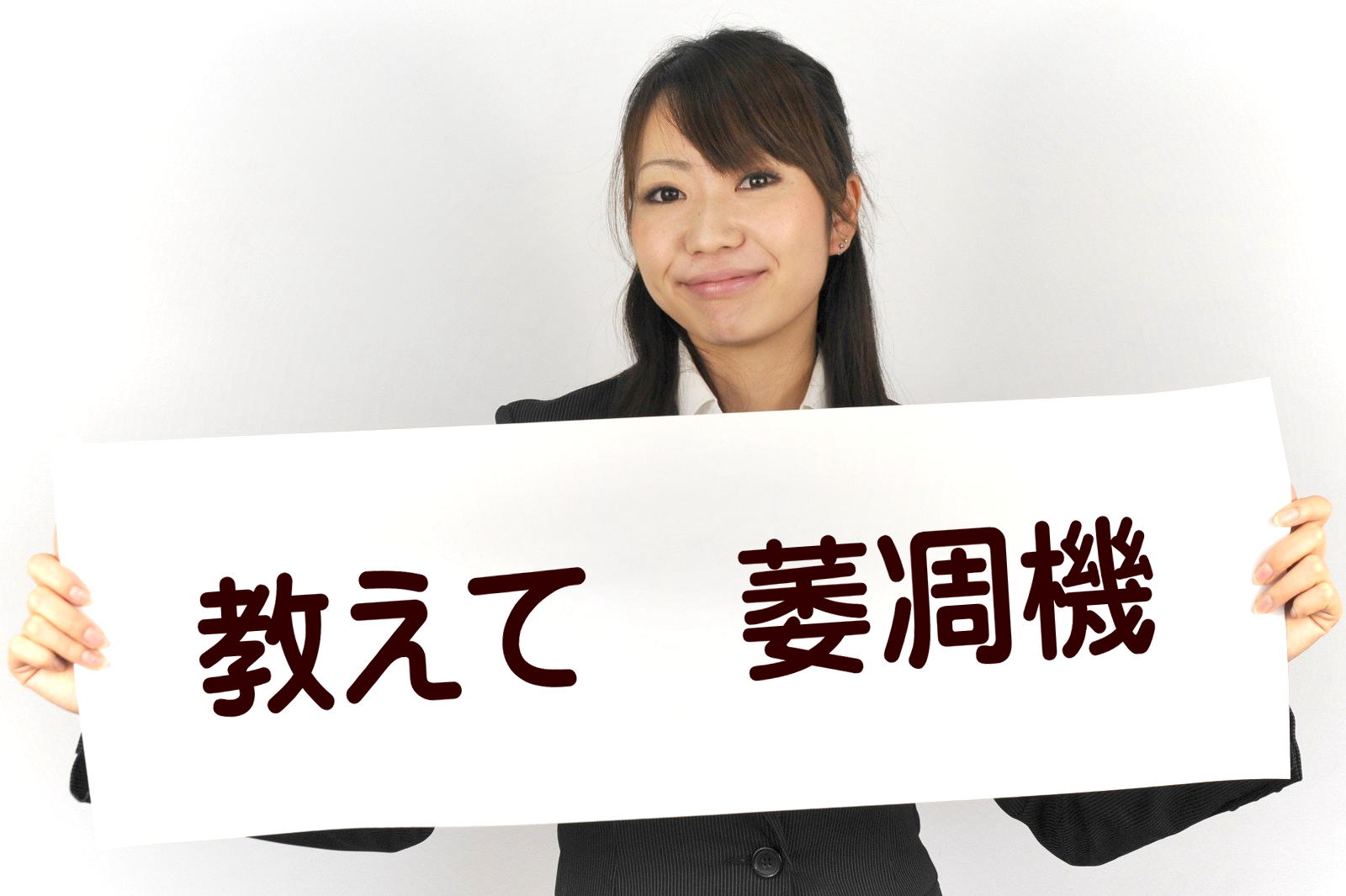 |
|
 |
次工程での加工のため、茶葉に含まれる水分量を調節する工程のこと。摘んだ茶葉に最初に行う行程である。実際には、萎凋棚に生茶 葉を広げ、通風環境下で静置する。これにより、茶葉は柔軟になりこの際 萎凋香(いちじく様の香りといわれる)を生じる萎凋の状態で、紅茶の香りや水色が変わる大切な行程のことをいいます。日本の茶葉は海外の品種と違い葉肉が薄く、地域により気温や湿度も違うので非常に難しいといわれている |
 |
基本は静萎凋となるが、日本においてはスペースが少なく、より小さな面積で行う必要がある。積んだ葉は下と上で風の当たりが違わないように注意し、まんべ んなく同様に萎凋が進むようにする必要があります。茶葉に傷がつくとそこから酵素が働き始めるため気をつける必要がある。品質を考えると、気温温度は40℃以下、茶葉の温度35℃以下に保ち、ゆっくり萎凋が均等に進むようにすることが重要とされている |
 |
通常茶葉の重量が元の茶葉の55%に減少するまで行うとされているが、一般に香りを重視する場合は萎凋を強く、水色を重視する場合は萎凋を弱くさせる方がよいといわれます。ただし茶葉の表面の水分のみ減らすのではなく茎や芯水が抜けることが必要なため、茶葉の茎を手で折り曲げ、柔らかい内は萎凋が不十分だともいわれます |
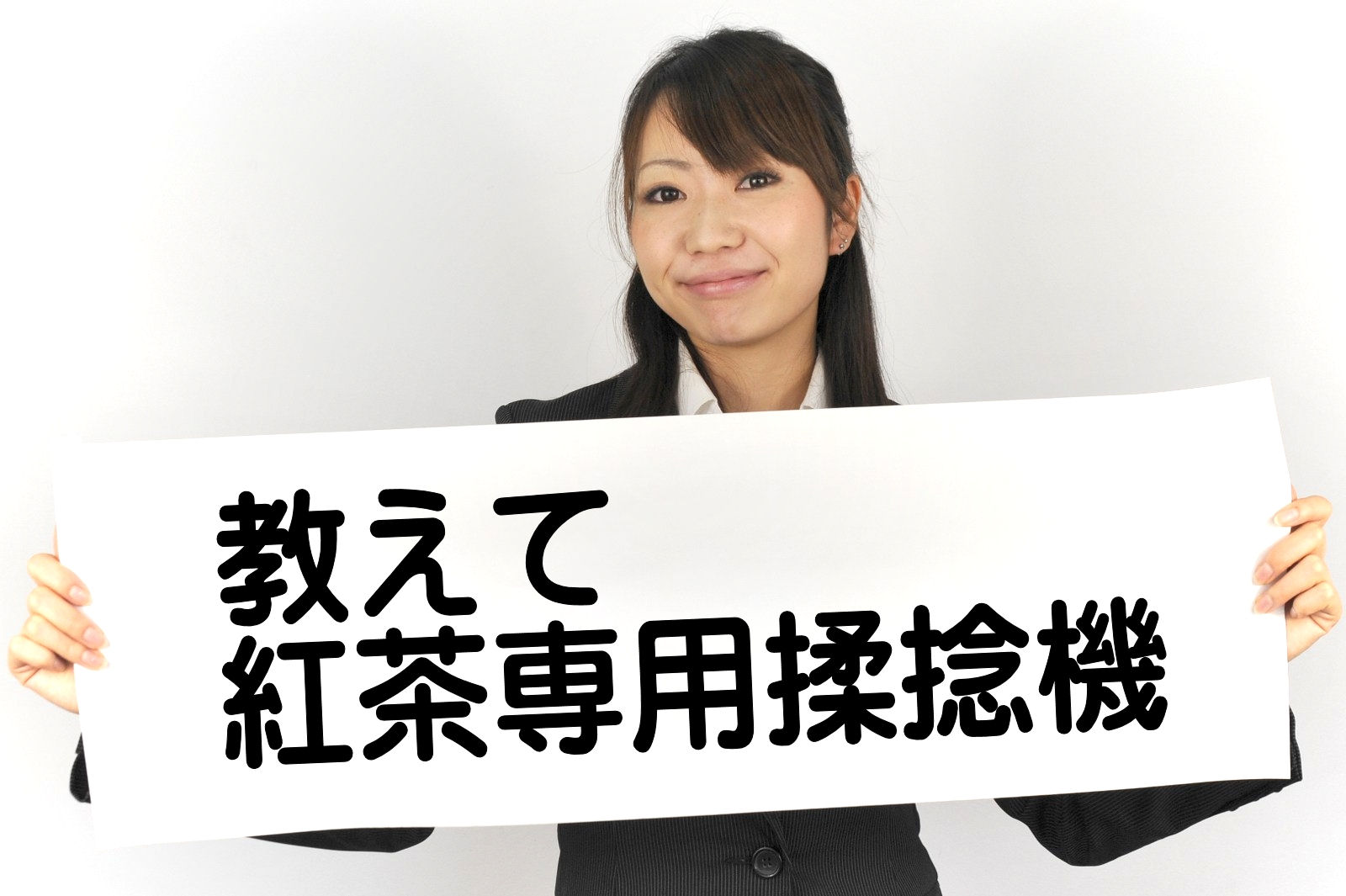 |
|
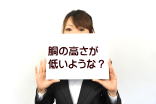 |
過去の経験から、茶葉が胴の中で回転(撹拌)されないと、胴の真ん中の層にある茶葉が蒸れて(酸欠)均一な発酵が難しくなってしまうんです。そこで、ダ テックの紅茶揉捻機は胴の直径と高さの比率を割り出し、現在の形になっているのです。胴の高さが高いほど撹拌効率は悪くなってしまいます。圧をかけて回転 していくので、なおさらのことですね。また緑茶でいう120Kのタイプも製作していましたが、より良い紅茶を製造することを考えて現在は60K以下の大き さをおすすめしています |
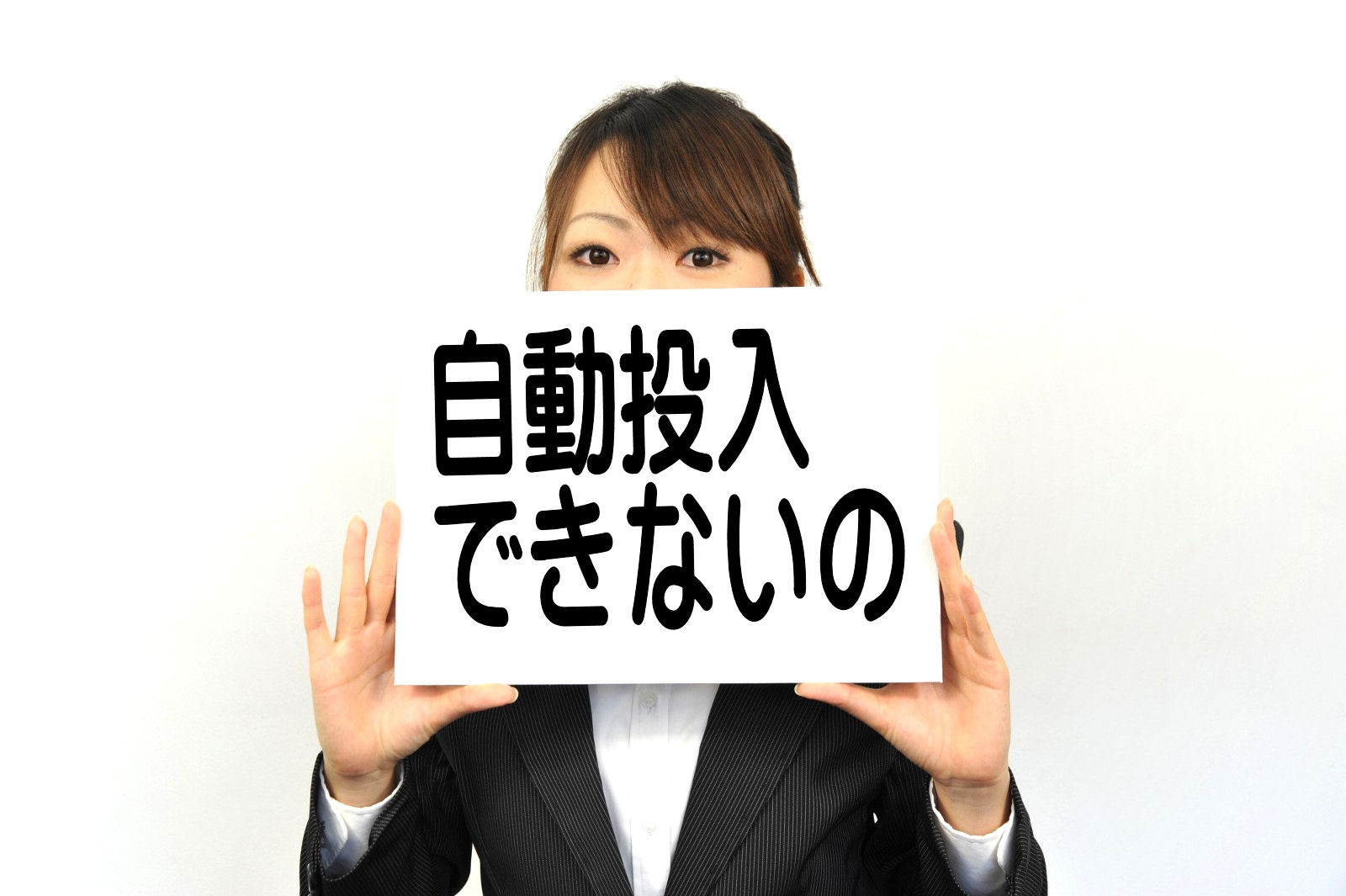 |
紅茶の揉捻時間は平均70〜90分くらいです。茶葉を投入するのもその時間に1回となるわけです。緑茶と違い、連続で流れていくお茶作りは基本的にしませ ん。ですからわざわざ大金をかけて自動化してもあまり意味がないと考え、標準では自動投入しない仕様になっています。もちろん、希望があればできますが。 それにもう一つ理由があります。それはスリランカやインドのような気候であればある程度均一に流れていきますが、朝昼晩と気温差が激しい日本ではいつでも 同じ条件で作ることが難しいからです |
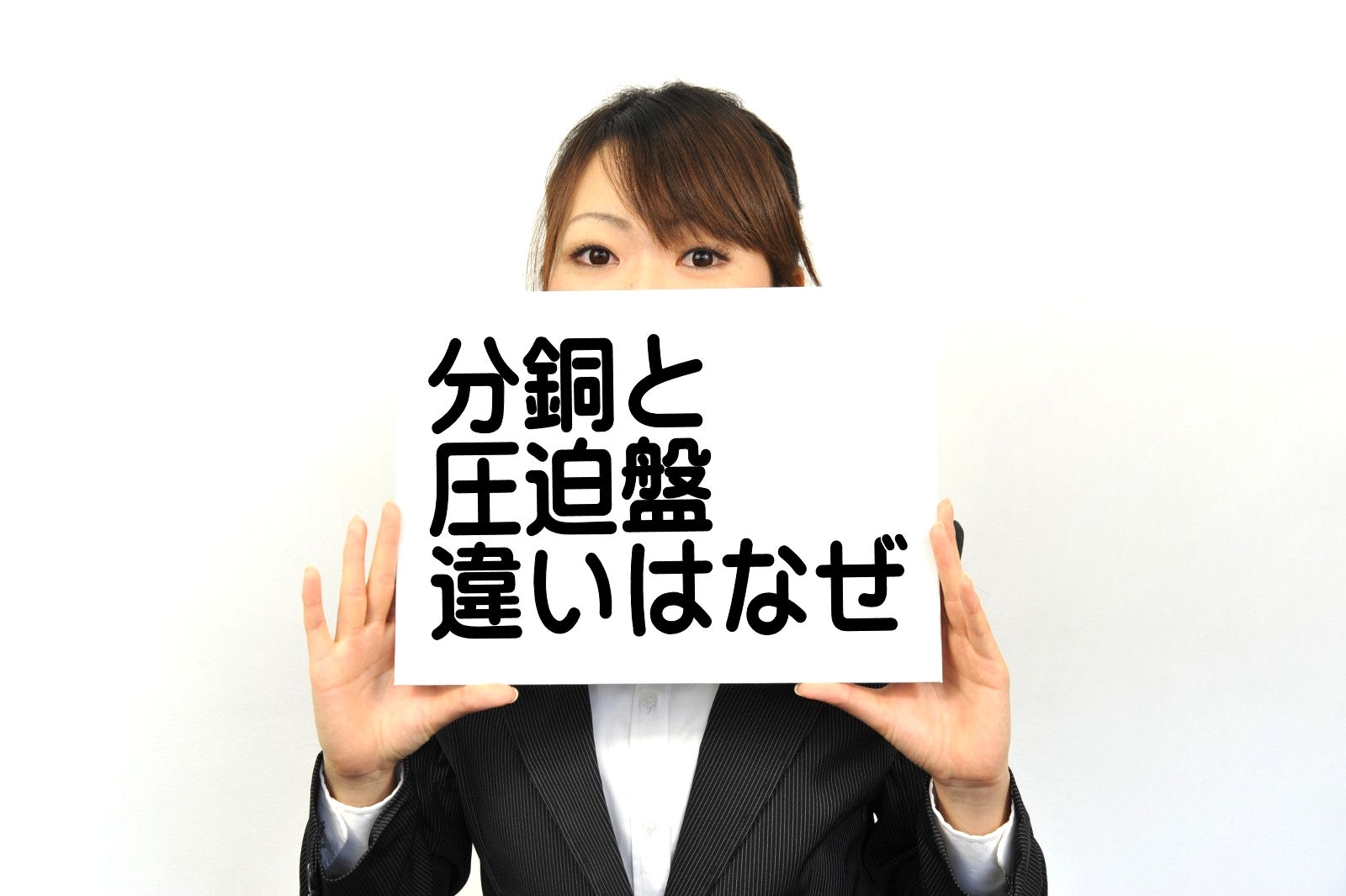 |
前述の通り、緑茶と紅茶の揉捻には製造方法の違いがあります。いわゆる緑茶の揉捻機は回転によってできる水分の均一化を目指します。茶葉が丸められ細かく なれば分銅を手前にしていきます。紅茶の場合茶葉を砕く必要から、おもりを乗せるのではなく圧をかける必要があるのです。そのため加圧式のフタがいるので す。でも茶葉に酸素も与えてやる必要があるので、当社の揉圧盤はスプリングをつけることにより動きをスムーズにするダブル圧迫式となっています |
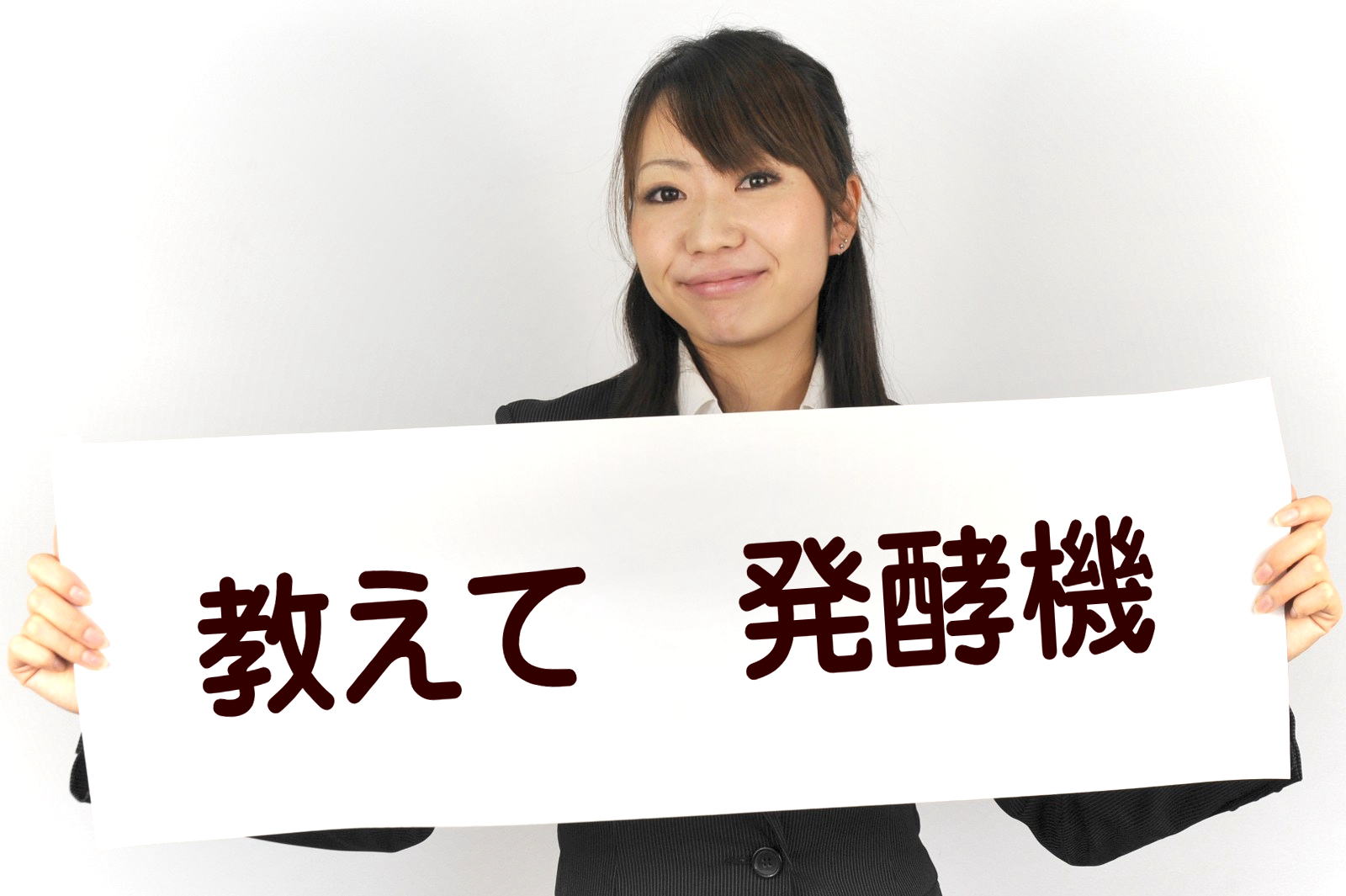 |
|
 |
発酵に必要なのは空気(酸素)と水(水分)と酵素です。 茶葉の発酵は厳密に言うと萎凋段階から静かに始まります。揉捻機で細かく砕かれることによってより発酵が始まります。これは茶葉の持っている過酸化酵素の 働きによります。この酵素は空気に触れることで分解を始めます。カテキンなどの酵素は金属と接触するとよりいっそう発酵が進みます |
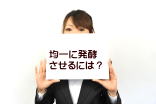 |
まず大切なことは、茶葉の状態(萎凋、揉捻後の茶葉)が均一であることです。このことなしに 均一な発酵はあり得ません。次に茶温をあげないこと。茶温が40度を超えると香気、水食ともに非常に悪くなります。最後に湿度。75%以上はほしいです。よく行われていた方法として、箱に揉捻後の茶葉を入れ、上に蒸しタオルをかぶせる方法。途中で茶葉を撹拌するのですが、発酵ムラができ、何杯も繰り返 すうちに発酵の度合いが変わっていたりしやすいです |
 |
発酵機の役割は茶葉を均一に発酵させることにつきます。 よく発酵機を使うと早く発酵しますか?という質問があります。これは発酵の意味を取り違えたものです。確かに熱を加えたりすれば発酵は早まります。しかし これは酵素の働きを無理矢理早くさせているもので、おすすめしません。本来の発酵という現象を助けるのが発酵機の役目なのです。湿度、温度を管理し最適な条件の下で茶葉の発酵を助け、均一な発酵を促進するものです |
バナースペース
ダテック
〒421-0204
静岡県焼津市高新田607-1
TEL 054-622-7757
FAX 054-622-7757